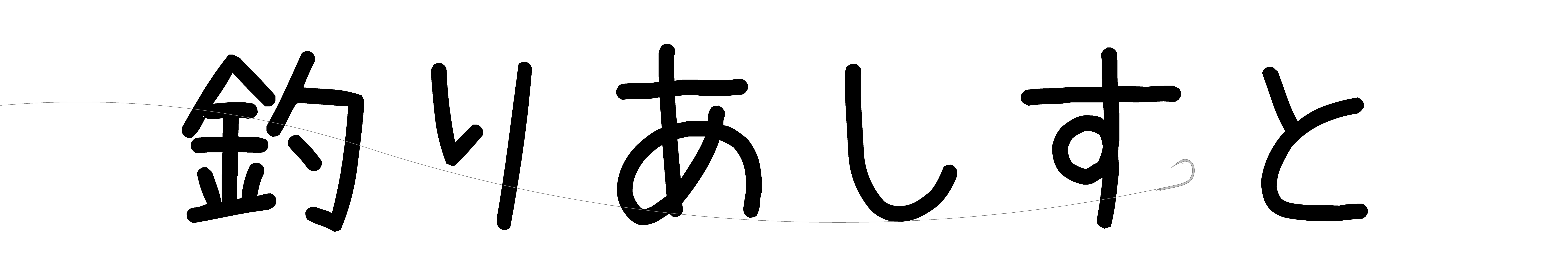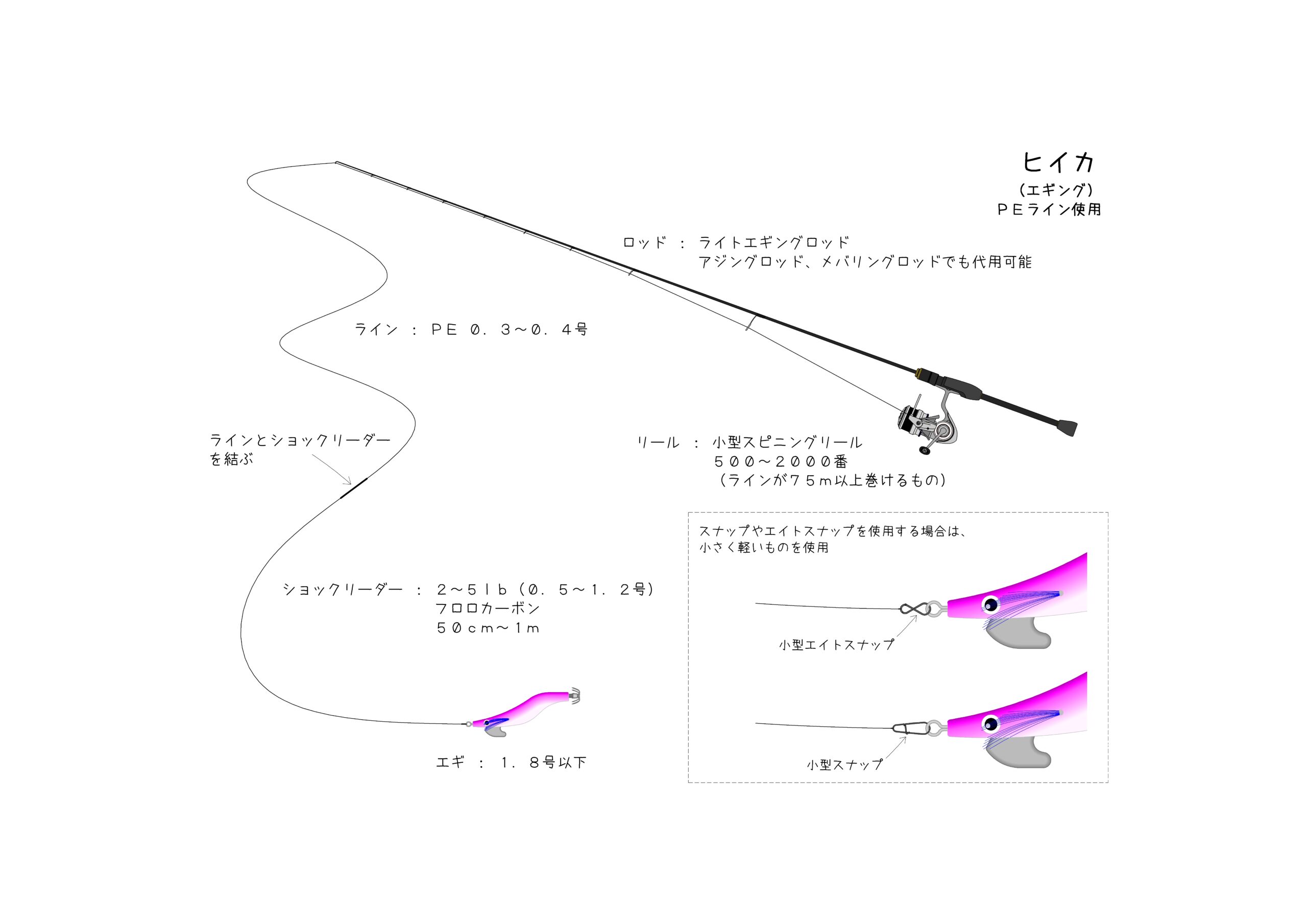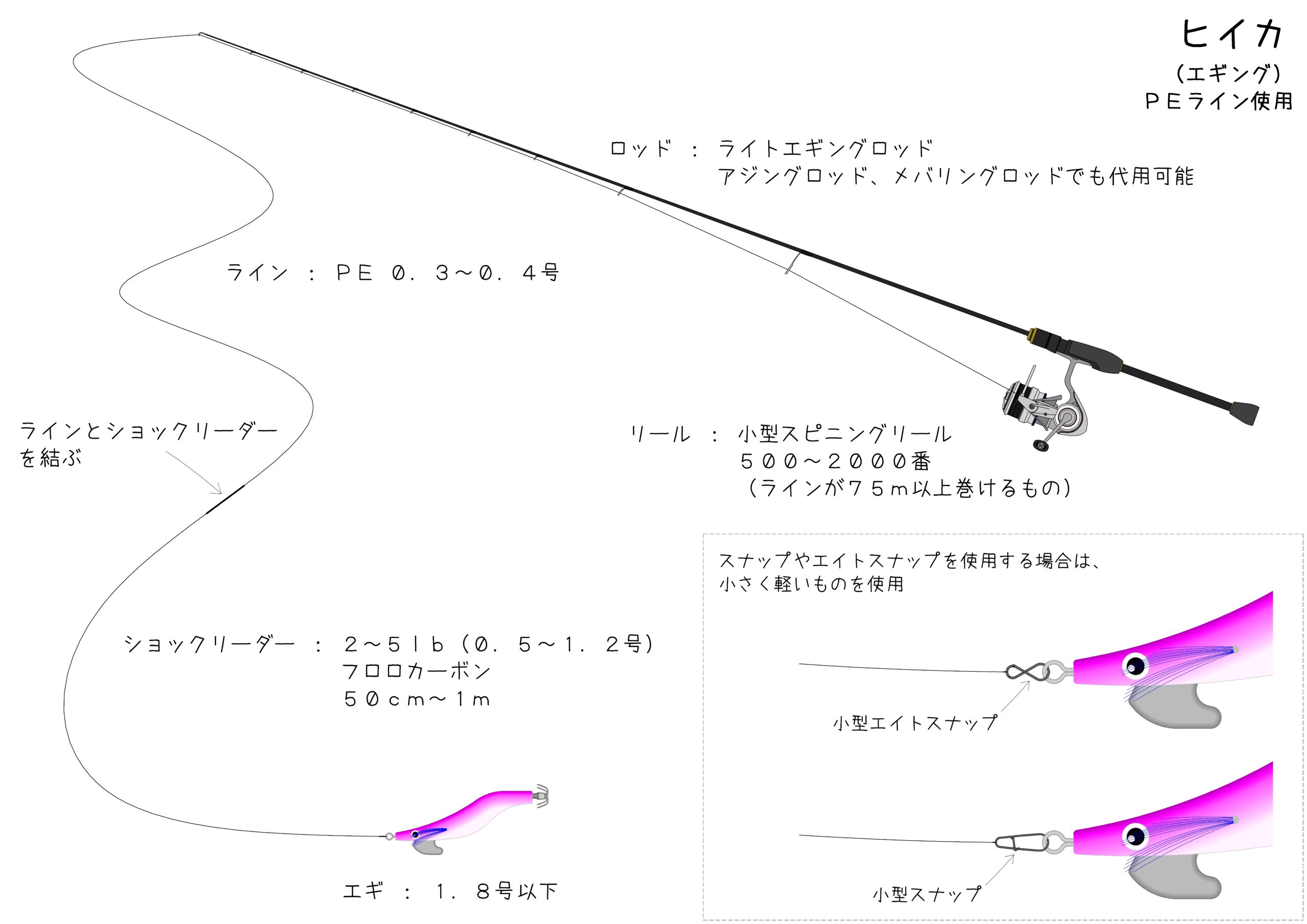ヒイカエギングの基本的なタックルです。(イラストをクリックすると拡大して見る事ができます)
ヒイカは手のひらサイズの小型のイカで、都心から近い港でも狙う事ができる身近なターゲットです。釣り方は「エギ」という疑似餌を使用したエギングや、活きエビを使用したウキ釣りで釣る事ができます。
夜釣りがメインになり、シーズンにもなると人気のあるポイントではヒイカ狙いの釣り人で賑わっている場所もあります。
イカ釣りの中では比較的簡単に釣る事ができますが、腕や経験で釣果に大きく差が出てしまう釣りです。
釣果を伸ばす為には相手を知る事が大事です。と言う事でヒイカの紹介です。
ヒイカってどんなイカ?
ヒイカは正式和名を「ジンドウイカ」と言います。
大きさ
- 胴体部が12cm程にまで成長する小型のイカ
生息域
- 水深50mより浅い穏やかな砂泥底の内湾
捕食している生物
- 小魚
- 甲殻類
- プランクトン
特徴
- 寿命は1年
- 日中は中層より深い場所に生息、夜になると水面付近までやってくる
- 10mより浅い場所で産卵
- 数匹~数十匹ほどの小さな群れを作る
- 光に集まる習性がある
- 夜の方が釣りやすい
釣りでの注意点
- アオリイカエギングのような大きなアクション(シャクリ)は必要なし
- エギに墨が付いていたら、必ず落とす
- イカが掛かったらラインを たるませない
- 大雨などで濁りが多い状況では釣る事は難しい
釣りのシーズン
- 東京湾周辺は11~12月
- 北九州は7~8月
狙う水深
- 日中は底~中層
- 夜は底~表層(イカの姿が見えていれば表層)
産卵期
- 春~夏
旬
- 特になし(1年中 味は落ちない)
リール
リールの種類
- スピニングリール
リールには「ギア比」があり、数値が大きいとリールのハンドル1回転でラインを巻き取れる長さが長くなります。リールにパワーが必要な場合はギア比の小さいリールを、エギを素早く回収し手返しよく釣りをする場合や、糸フケを素早く取りたい場合などはギア比の高いリールを使用します。
エギングは、素早く糸フケを取る事のできるギア比の高いリールがオススメです。
リールサイズ
- 使用する道糸が75m以上巻けるもの(PE0.3~0.4号)(ナイロン、フロロカーボン3~4lb)
PEラインとナイロン、フロロカーボンラインは同じ強度でも太さが違う為、使用するラインによってリールのサイズが変わります。
- ダイワ(PEライン) : 1000~2000番
- ダイワ(ナイロン、フロロカーボン): 1000~2500番
- シマノ(PEライン): 500~2000番
- シマノ(ナイロン、フロロカーボン): 500~2500番
※各メーカーでシャロースプールモデルなど、同じ型番でも糸巻量が違うものがあるので、購入の際は糸巻量を確認して下さい。
入門用オススメリール
価格が抑えられた釣り具大手メーカー(ダイワ)のこの釣りに向いているスピニングリールです。多くのスピニングリールのハンドルは、右巻き、左巻きのどちらにも自由に変えられる特徴があります。
中級クラス オススメリール
初心者向けリールより基本性能が高く、耐久性も上がっている為、少し高性能なリールが欲しい、長くリールを使用したい方などにも向いています。
高性能オススメリール
最高性能のスピニングリールです。性能重視の為、価格は高額になってしまいますが、ドラグ性能、ハンドルを回した時の滑らかさなど、様々な面でトップクラスの性能を誇っています。
ロッド(竿)
最適なロッド
- ヒイカ専用ロッド
- ライトエギングロッド
代用可能なロッド
- アジングロッド
- メバリングロッド
アジングロッドやメバリングロッドを使用する場合、エギの重量は1.5号で約4g前後、2号で9g前後なので、使用できるルアーの最大重量が10~14g程のロッドがオススメです。
ルアーロッドの場合、長さはft(フィート)とinch(インチ)で表す事が多く、以下のような計算方法になります。
- 1ft=30.48cm
- 1inch=2.54cm
- 1ft=12inch
- 例 9.6ft=(30.48×9)+(2.54×6)=289.56cm
- 例 7.11ft=(30.48×7)+(2.54×11)=241.3cm
そして、ロッドには使用できるルアーの重量やエギの号数、アクションが記載されています。アクションはロッドの硬さで、ルアーロッドで主に使われている表記は以下のようになります。
- UL(ウルトラライト)
- L(ライト)
- ML(ミディアムライト)
- M(ミディアム)
- MH(ミディアムヘビー)
- H(ヘビー)
UL(ウルトラライト)は柔らかめ、L(ライト)→ML(ミディアムライト)→M(ミディアム)→MH(ミディアムヘビー)→H(ヘビー)と徐々に硬くなります。
使用できるルアーの重量とアクションは関係性があり、一般的なロッドではアクションがUL(ウルトラライト)などの柔らかいロッドは、軽いルアーは扱いやすいけれど、重いルアーは投げる事すら困難です。H(ヘビー)などの硬いロッドは、重いルアーを使用できるようになりますが、軽いルアーは扱いにくくなります。
ヒイカのような小型のエギを使用する釣りの場合、エギングロッドはUL(ウルトラライト)、アジングロッドやメバリングロッドはML(ミディアムライト)~M(ミディアム)が向いています。
入門用オススメロッド
価格を抑えたヒイカ釣りに向いている初心者向けロッドです。
ヒイカ専用ロッド
数は少ないですが、ヒイカ専用ロッドも販売されています。
高性能オススメロッド
釣り具大手メーカー(ダイワ)のヒイカ釣りで使用する事のできる高性能ライトゲームロッドです。性能重視の為、価格は上がってしまいますが、軽く感度が優れている事が特徴のロッドです。
ライン(道糸)
素材
- ナイロン
- フロロカーボン
- PEライン
素材については主にナイロン、フロロカーボン、PEラインの3種類ありますが、それぞれ以下のような特徴があります。
ナイロンラインの特徴
- 価格が安い
- 糸グセはフロロカーボン製より付きにくい
- 扱いやすい
- 伸縮性がある為、衝撃を吸収できる
- 感度は劣る
フロロカーボンラインの特徴
- 根ズレや擦れに強い
- 比重はナイロンより重い(沈みやすい)
- 透明度が高い
- 伸縮性はナイロンより少ない為、感度が良い
- 糸グセが付きやすい為、扱いにくい
PEラインの特徴
- 糸グセは、ほぼ無し
- 他のラインより飛距離を出せる
- 伸縮性は、ほぼ無し
- ラインの中で一番高感度
- 価格が高い
- 根ズレに弱い
- 熱に弱い(結ぶ時の摩擦熱に注意が必要。摩擦熱を発生させないようにゆっくり結ぶ)
号数(太さ)
- PEライン : 0.3~0.4号
- ナイロン、フロロカーボン : 3~4lb(0.8~1号)
長さ
- 75m以上
リーダー
PEラインを使用する場合は、ナイロンかフロロカーボン製のリーダー(ショックリーダー)を使用します。PEラインは根ズレに弱く透明なものがありません。この弱点を補う為にリーダーが必要になります。
素材
- ナイロン
- フロロカーボン
号数(太さ)
- 2~5lb(0.5~1.2号)
長さ
- 50~100cm
イカは目が良い為、透明度の高いフロロカーボン製のリーダーがオススメです。
リーダーの結び方
PEラインを使用したエギングではPEラインとリーダーを結ぶ事が必要不可欠です。色々な種類の結び方がありますが、ヒイカエギングでは簡単なトリプルエイトノットがオススメです。
トリプルエイトノットの結び方はこちらへ
これだけは覚えておきたいライン(釣り糸)の結び方 ラインとライン編
エギ
- 1.3~1.8号を使用
夜、ヒイカは水深が浅い場所にも平気で泳いできます。水深が浅いポイントを狙う場合は、できるだけ沈下速度の遅いエギを使用すると根がかりのリスクが減り、釣りやすくなります。
そして、同じエギの号数でもいくつかの重さのエギが存在します。
エギメーカー大手のヤマシタのエギを参考にすると・・・
ナオリーRH 1.5号でも3種類存在します。
- シャロー 重量:3.0g 沈下速度:15~18秒/m
- ベーシック 重量:3.5g 沈下速度:5.0~5.5秒/m
- ディープ 重量:6.0g 沈下速度:2.5~3.0秒/m
この様に、同じ大きさの1.5号でも、重量と沈下速度に大きな違いがあります。水深が1mも無い場所で、ディープタイプを使用すると、根がかりのリスクが増え、扱いづらいです。
水深が浅い場所やヒイカの姿を見る事ができる場合は、シャロータイプのエギがオススメです。
スナップ
スナップを使用する事で、エギの交換が簡単にできるようになります。しかし、エギが小さい為、シーバス用などの大きなスナップを使用してしまうと、スナップの重さでエギのバランスが崩れてしまう可能性もあります。
ヒイカエギングでは、できるだけ小さく軽いスナップが向いている為、メバリング用などの小型スナップやエイトスナップを使用します。
便利グッズ
投光器
ヒイカは光に集まる習性があり、港に設置されている常夜灯の下は良く釣れる為、人気があり、場所を確保する事が難しいと思います。
灯りの無いところに灯りを作ればいいのですが、手持ちのLEDライトでは光が弱い・・・。かと言って、発電機と投光器を準備するとなると、設備が大掛かりなものになり、お金も掛かってしまいます。
そんな時に活躍するのがバッテリー式LED投光器です。
投光器の光は広範囲に広がるものが多く、海面を広く照らす事ができます。そして、最近のLED投光器は、小型化、薄型化、軽量化され、防水タイプもあり使い勝手は上がっています。
現在、市販されている最強クラスの光量のバッテリー式投光器はこちら
釣りのコツ
- ヒイカが見える時は水面付近、見えない場合は水面~底まで広く探る
- エギのアクションは小さめでOK
- フォール中(エギが沈んでいる状態)は常にラインを張る
注意点
- エギにはカエシが無い為、イカが乗っている(針に掛かっている)状態ではラインをたるませない
- エギやライン、リーダーに墨が付いていたら、ブラシ等でキレイに取る
釣れない場合の確認ポイント
釣り場
水深の浅い穏やかな砂泥底の内湾がポイントになります。
初めて行く場所などでは、事前に地元の釣具屋などで情報収集をしましょう。
狙う水深
ヒイカの姿が見えない場合は水面~底まで広範囲に探りますが、低活性時などは中層~底付近にいる事が多いです。
エギ
イカは沈下速度の遅いエギの方が釣りやすいです。浅いポイントでは、その傾向が特に強い為、沈下速度の遅いエギがオススメです。
カラーについては、他のイカに比べ、そこまで大きく影響はありませんが、同じエギを使い続けているより、いくつかのエギをローテーションした方が釣果は上がります。
エギのアクション
アオリイカのエギングのような派手はアクションは必要ありません。
竿先で「ちょん」と動かしてアタリを待ち、「ちょん」と動かしてアタリを待つの繰り返しです。動かす時のイメージは、エギが数センチメートルだけ素早く動く感じです。
アワセのタイミング
ヒイカは小さい為、ヒイカがエギを触っている状態でも、感じ取る事ができない場合もあります。しかし、ヒイカが見える所を泳いでいる場合はチャンスです。エギを常に目視で確認し、手元に何も感じなくても、エギが横や沖の方向に動き出した時がアワセのタイミングです。
フィッシュイーターの存在
夜釣りでは、投光器を使用する事でヒイカを集める事ができますが、同時にヒイカを捕食するシーバスやタチウオなどのフィッシュイーターも集まってくる可能性があります。
フィッシュイーターが近くにいると、光に集まったヒイカは散ってしまいます。
フィッシュイーターの姿が見えた場合は、投光器を一時的に消す、又は投光器を使用しない方がいい場合もあります。
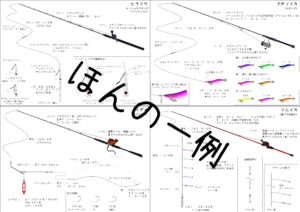 タックル・仕掛け一覧
タックル・仕掛け一覧